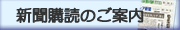今年度、「21世紀・新しい時代の健康教育推進学校」は、全国の学校保健会より82校が推薦。最優秀校4校、優秀校12校、特別奨励校2校、優良校64校が選ばれた。そこから最優秀校の実践を紹介。
人として生きる基本となる
“心と体の健康教育”の推進
東京・渋谷区立 常磐松小学校
 |
給食指導で |
渋谷区立常磐松小学校(小野ヒサ子・校長)の健康教育は、教育計画において、「すこやかタイム(総合的な学習の時間)」「その他の特色ある活動」を主に、各教科領域などと連携して位置づけている。
「すこやかタイム」は、年間17時間。年度当初に「自分にぴったりの健康のめあて」を児童に立てさせ、めあてごとの異学年集団による活動、「健康めあて集会」「健康めあて振り返り集会」を年4回実施している。
「自分にぴったりの健康めあて」は、6年間継続してめあてに向かってすすんで努力する態度や継続する強い心もたせる学習として進め、児童が立てためあては、1年間を記録できるよう1枚の「めあてカード」にまとめる。めあての内容は、「生活習慣に関すること」「心に関すること」「目・姿勢に関すること」「歯に関すること」「食に関すること」「遊び・運動に関すること」。
同校は、また学校医とのつながりも深い。「はつらつ面談」では、肥満傾向のある児童を対象に毎月「はつらつ測定」を実施、保護者、養護教諭、学校栄養士とともに話し合いを持っている。「すこやかの会」は健康診断結果や健康状態の報告のほか健康のめあてへの取組み、疾病への対応、心の健康というテーマを設定し、取組みの成果や課題の検証、専門的な研修などが主な内容で、保護者、地域の人も参加して連携を図っている。
◇
健康な生活をめざした
自己教育力の育成
岡山・山陽町立 高陽小学校
 |
ヘルスアップ講座の一つ
「救急蘇生法」 |
山陽町立高陽中学校(花田文甫・校長)は、生徒数397名。学校行事や部活動が盛んで、また、職業体験やボランティア活動を通して地域や異世代との交流も積極的に行っている。
同校は健康教育実践の配慮事項として、全ての学校教育分野において、「報告・連絡・相談・共通理解・共通実践」を合言葉に風通しのよい、一枚岩の関係を重視している。また、学校医や地域関係機関等とも協力しあった人間関係つくり、地域の人材活用にも積極的に行っている。
重点目標への具体的な取組みとしては、生徒会活動から「レッドリボン運動」、ストレスを理解し、解消法について提案する「ストレスチェック」、「歯みがきコンクール」、朝食の重要性を呼びかける「朝食のすすめ」を行っている。また、地域人材活用事業として、「ヘルスアップ講座」(健康教育講座)を総合的な学習の時間に位置づけ、「救急蘇生法」「心の護身術」など健康情報を提供する7講座を実施、性に関する指導として「性教育講演会」も開催した。
◇
すこやかな体と
豊かな心を育む健康教育
愛知・小坂井町立 小坂井西小学校
 |
4年生「ぼくたちスーパーパワフル10歳だ」
で、命についての話を聞く |
小坂井西小学校(岡田正三・校長)は児童数702名、以前から健康教育に取り組んでいる同校は近年、心の面にも力を入れている。
同校の具体的な実践は、保健学習や学級活動において、担任と養護教諭、外部講師の協力を得て、「性の指導」などを課題に、取り上げ、これらは発展的な学習の場として位置づけている「あおい学習」につなげて、これまでに「やさいで元気」(3年生)、「ぼくたちパワフル10歳だ」(4年生)、「けがの防止」(5年生)、「小西ウイルスバスターズ」(6年生)などのテーマに取り組んできた。
また、この他に児童達が自主的に自分の得意な種目を選んで競い合う「わんぱくチャレンジ」や「駆け足運動」「短なわ、長チャレンジ」などの「わんぱくタイム」、「歯みがきの指導」「健康観察」、豊かな心を育てる実践として友達のよさを認め合う「よかったみつけ」、拡大学校保健委員会を含めて年5回開催した「小西すこやかサミット」(学校保健委員会)、家庭・地域を学校へ招く「学校へおいDAY」(学校公開日)を実施している。
◇
自己健康課題に気づき健康づくり
への実践ができる児童の育成
群馬・高崎市立 南八幡小学校
 |
夏休みの課題でつくる「親子環境新聞」。
学級で発表会を行い、掲示をしている |
高崎市立南八幡小学校(梅澤優幸・校長)は、児童数360名。同校の健康教育の推進は、学校保健委員会を中核とし、学級活動では、保健、安全、給食、性教育を柱に、特に歯と口の健康、性教育(エイズ教育)、喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育には担任と養護教諭のTTを実施、また、歯科衛生士や栄養士とのTT授業も取り入れ、総合的な学習の時間でも学年ごとに実施している。
具体的な取組みは、1.環境教育 2.学校保健委員会 3.家族会議 4.けんこうカードの活用 5.児童委員会活動 6.総合的な学習の時間 7.親子環境新聞 8.スポーツ活動 9.食に関する指導
2 は年に5回開催、そのうち1回を拡大学校保健委員会として保護者や学校評議委員も出席する。また、PTA保健委員が主体となった調査研究した内容を発表する回も設けている。
6 は環境と健康を2本柱に、健康教育では、「食」をテーマに地域で作られているトマト作りの学習(3年生)、助産師による命をテーマにした学習(4年生)、手話や車椅子体験、高齢者との交流(5年生)、「心」の学習(6年生)など。7は10年度から夏休みの課題として、健康づくりを阻害している環境問題はなにか、その解決には何が必要かなどを児童だけでなく家族で新聞にまとめている。
【2005年3月19日号】