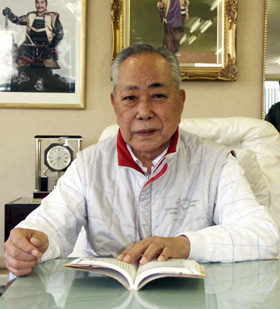体験学習特集〜江戸ワンダーランド 日光江戸村
江戸の歴史・文化を知り日本のよさを再確認
女性の強さや美しさを知る〜時代絵巻イベント「吉野太夫 東下り」
 |
手古舞を披露しながら村内を練り歩く |
 |
突然来襲した忍者に立ち向かう |
修学旅行や遠足のなかで、体験型の学習が増えている昨今、「江戸ワンダーランド 日光江戸村」(栃木県日光市/野口勇会長)では、歴史に遊び、歴史を学べるカルチャーパークとして、多くの学校利用や外国人観光客を受け入れている。時代考証に基づき再現された歴史体験施設や建造物の数々、そこで体験する日本の歴史と文化からは、日本の良さを再確認することができる。同村では、観光庁の10月発足を目指す日本の、歴史文化をさらに伝えるべく全村あげての時代絵巻イベント「吉野太夫 東下り」を開始した。江戸開府当時の史実に基づき、可能な限り忠実に再現したというこの一大イベントの見どころ、そして体験施設として人気を博す「社会学学問所」のポイントを紹介する。
江戸幕府開府当時、諸大名の武家屋敷建設に伴い、多くの家臣たちが江戸に集中した。さらに、全国から大量の労働者が流れ込み、不穏な状況下にあった。なかでも、単身赴任というなかで戦国時代の遺風を残した浪人たちのけんかは絶えずにいた。
そこで、時の征夷大将軍である徳川家康は、この状況を打開すべく武士専用の社交場、しかも大掛かりなものが必要と感じ、日本最大規模の吉原遊郭(旧吉原)の建設を命じた。
その宴席でおもてなしをする社交女性には、高度の教養と行儀作法、茶道・華道・茶の湯など諸芸百般を身につけることが必要とされており、最高級の女性には三千石以上の官位に匹敵する名誉と身分を与えた。これが吉原の「太夫」の始まりと伝えられている。
この吉原は、明暦の大火を境に浅草に移り新吉原と呼ばれ商人たちの社交場となり一般的になっていくが、今回のイベントでは、旧吉原における武家専用の奥ゆかしい存在であった時代の「太夫」をクローズアップし、江戸の「太夫」たちに美しいもてなし方を指導するために京から招聘された「吉野太夫」の東下りの様子を再現した。
再現にあたっては、同村らしいエンターテインメント性を組み込んでおり、豪華絢爛の紗の衣装に身を包んだ吉野太夫が輿に乗り村を練り歩き艶やかな手古舞を披露する一方で、武道にも練達した吉野太夫が忍者の急襲に立ち向かう華麗な錫杖アクションなど、見る者を飽きさせることないパレードとなっている。
 |
日本伝統文化劇場でのお芝居 |
また、日本伝統文化劇場内で行われる花魁ショーでは、吉野太夫が吉原で活躍する様子が描かれており、東下りと併せて見ることにより、より一層日本女性として諸芸を身につけた強さや美しさ、「太夫」としての責任を深く理解することができる。
さらにそのショーのなかでは、観客席からも舞台に選ばれるという演出があり、見るだけではなく場内が一体となった参加型のショーとなっており、見終わった後は満足感でいっぱいになることだろう。
会長インタビュー/新イベントのみどころと日光江戸村の役割
50数年間の”太夫”の活躍 隠れた歴史を知って欲しい
|
代表取締役会長 野口 勇さん |
江戸ワンダーランド日光江戸村では、観光立国日本の推進にあたり、タイ・シンガポールをはじめとした東南アジア諸国にPR活動を進めるなど、日本だけに留まらず、諸外国からの観光客に日本文化の魅力を紹介すべく、さまざまな活動を行っている。一大イベント「吉野太夫 東下り」に対する熱い思い、そして今後の同社における活動について野口勇代表取締役会長に伺った。
全村をあげた一大時代絵巻イベント「吉野太夫 東下り」の歴史的背景を教えて下さい
徳川家康公が関東に入府して来た時は、武蔵野は猪や熊のでるような場所でした。豊臣秀吉公は東海道を広く支配していた家康公を、箱根の山を越えることも困難な関東に追いやってしまおうと考えました。家来たちが反対するなか、家康公は涙を飲み関東に入ることを決めたのです。秀吉公は関東がどのようなところか分かっておりませんでしたが、家康公はよく理解しており、非常に広い関東平野を開発すれば、必ずや力をつけることができると考えておりました。
土地を開発していくためには、大勢の侍や農民が関わってきます。開発していくうちに、関が原、大阪冬の陣・夏の陣と家康公は天下をとっていくわけですが、そのうち、人質として諸大名たちの家族を江戸に住まわせることを考えました。大名たちは江戸に大きな屋敷を構え、そして街並みができ、家来たちも江戸に入ってきます。
そうしたところ、江戸がごったがえしけんか口論が耐えない状況になりました。その状況に困り、治安の維持を考えていたところに、秀吉公と共に戦った大名たちの下にいた浪人たちも江戸にやってきました。それら浪人たちは、隙あらば徳川幕府をつぶしてやろうという考えの者たちです。
そこで家康公は、かつて秀吉公に招かれて京都に行ったことを思い出しました。京都には茶道・華道といった女性の諸芸百般、加えて武芸までできる「太夫」がおりました。そのすばらしさを知っていた家康公はぜひ江戸にお迎えしたいと考えました。その時招いたのが「吉野太夫」でした。
そこで、吉原という武家専用の社交場をつくりました。当時の吉原は「色香は売っても体は売らない」という品格のあるもので、太夫は官位でした。その頃、2代将軍秀忠公は、諸大名の取り潰しを行っておりました。親族から始められた取り潰しは、潰せば潰すほど浪人がはびこり、幕府へ反感を持つ人が大勢増えていきました。そこで必要になったのが情報です。
太夫は1か月に一度江戸城にあがり、お茶を一服するという名の下、吉原で集めてきた情報を老中が聞くということが行われていました。その情報を得て、当時長い間大目付を行っていた柳生一族が忍者を各藩に配置して情報の裏づけを取った上で、大名の整理をしていきました。そうして幕府は益々力をつけていくのですが、そういう意味で太夫という役職は非常に活躍の場があったわけです。
明暦の大火まで続く旧吉原の歴史
〜その活躍を知ってもらうため、このイベントを始めたわけですね
明暦の大火まで50年もの間、太夫は活躍しました。大火の後吉原は浅草に移され、新吉原として新開地となっていきましたが、大名らは江戸の建て直しにより財力を失って疲弊し、それに代わって材木屋の紀伊国屋文左衛門らといった商人らがもうけていきます。こうして新吉原は一般のものとなり、太夫という官位はなくなり、それに代わって我々がよく耳にする「花魁」が生まれました。
50数年間の太夫の活躍により、400万石であった徳川幕府は800万石となり力をつけていきました。
このように幕府から官位をいただいて、お席にはべっていた太夫がいるわけですが、一般の方はそういう歴史を知りませんので、隠れたその歴史を知っていただきたいと思っております。
〜イベントの見どころを教えて下さい
ショーのなかでだいたいの説明はしておりますが、実はその後があり、それは日本伝統文化劇場につながっていき、そこでお芝居が展開されます。その中では吉原に通い続けた水戸光圀公や、招かれた伊達政宗公が出てきます。そこに亡藩の残党が斬りこんで来ますが、太夫は「吉原は太夫の城です」と立ち向かい場を収め、最後は太夫の踊りで終わります。そこまで見ることで、全ての話がつながっていきますのでぜひ劇場まで足を運んでいただきたいです。
日本文化を知る人材を育てて
〜体験学習の場として利用する学校も多いようですが「江戸ワンダーランド日光江戸村」の持ち味はどこにありますか
私どもの売りは江戸の文化です。江戸時代全般にわたって開府当初からお披露目していくべきだという考え方になりまして、今回のイベントにもつながっていきました。家康公は、老人や親を大切にすること、礼儀を重んじることに力をいれる学問の神でもありました。社会学学問所では、そういった教えを学ぶことができます。
我が国では現在、観光庁発足の準備をしております。これまで国は観光立国としての活動ができずにいましたが、観光庁ができることによって日本文化の宣伝ができるようになります。日光には世界遺産に登録された日光東照宮もありますから、世界から観光客が日本に来やすくなります。日本文化を宣伝できる我が社としては、これを全面的にバックアップしていきたいと思っています。
〜それら日本の文化を担う子どもたちを預かる先生方へのメッセージをお願いします
観光立国として日本を栄えさせるためには、観光の専門的な職員を養成する学校が必要になります。一科目としてではなく、今こそそういった専門的な学校を作るチャンスです。観光庁が発足することで日本に大きな柱ができます。
また、そのような学校を作るには、日本文化をよく知っている人材を作っていかなくてはなりません。先生方にも日本の文化を知り、学校もそういったことを教えることに力を入れて欲しいと思っています。
我が社でも外国人観光客へ向けた対応として、広く優秀な人材の育成や募集に力を入れており、まず、英語、韓国語、中国語の3か国語を全職員に勉強させていこうとしております。
「今こそ取り戻せ、日本の心!」寺子屋や昌平塾などを再現
正座で社会規範を身につける
 |
寺子屋で書道の練習 |
 |
竹とんぼを手作りする |
 |
輪になってお手玉を作る |
村内では「今こそ取り戻せ、日本の心!」をモットーに、「学」「創」「遊」「食」の観点から「社会学学問所」を用意しており、子どもたちが歴史と文化に触れられる。
ここではまず、頭から足の先まで当時の衣装に着替えることから始まる。そして、日本の江戸時代に庶民の教育機関として普及した「学問所 寺子屋」が再現されており、正座をしながら格言や中国の古典などの教えなどを学び、社会規範を身につける。
「体験工房」内では、自分たちで遊び道具を作ることができる。ここでは創意工夫力を養うこと、そして「物」を大切にする「心」を育むことができる。そこで作った竹とんぼやお手玉などは、村内で仲間たちと共に遊ぶこともでき、人間関係を学ぶ大切な場ともなる。
また、食事に関しても自然の素材を生かした当時の料理を再現している。江戸時代の食事は質素なものであり、押麦・稗・粟などの穀物を主食としていた。それらは繊維質が多く、腸の働きを助ける優良健康食であり、安全でおいしく栄養バランスも整っている。同施設では、食事は人間の生命を養い健康を維持するためのものであるとして、「きこり鍋セット」(2種類)を提供している。
【体験学習料金】
小学生・中学生/3000円。体験学習料金には、通行手形(入村+全ての劇場・体験館のフリーパス込み。遊戯施設は除く)・時代衣装一式のレンタル及び着付け・学問所での受講・江戸時代の遊具づくりと遊びの体験が含まれている。
※20名以上から受付(要予約。食事は100食まで)
【食事内容・料金】
きこり鍋セット・1260円、きこり鍋セット特別コース・1575円