生活クラブ生活協同組合・神奈川など8団体からなる国際協同組合年フォーラム実行委員会は、2025年が国連の定めた国際協同組合年であることから、子供・若者の不登校や自死が増え続ける問題意識をテーマに「2025国際協同組合年フォーラム」を7月7日(月)、横浜の関内ホールで開催した。
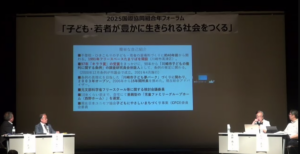
パネルディスカッションのようす
<基調講演>
「どうでもいい命」が口ぐせのA子
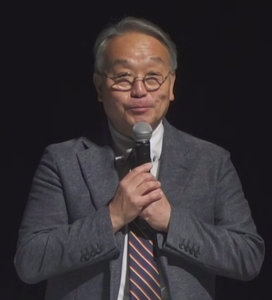
講演を行う奥田氏
奥田氏の基調講演では「『ひとりにしない』という支援~抱樸の子ども支援から~」をテーマに語られた。奥田氏は北九州市でホームレスや子供の支援など29事業を展開。奥田氏は10年前に当時20歳だったA子と出会った。何度も自殺を図ってきたA子を抱樸で引き取ることにしたが、出された食事を目の前でゴミ箱に捨てるなど問題は尽きなかった。
A子の口ぐせは「どうでもいい命」だったが、恋人ができるとA子が笑顔を見せるようになった。しかし、半年後に彼は原因不明の死を遂げてしまう。そのことをA子に告げると急に飛び出してしまい、見つけた時は呆然自失の状態だった。
その1年後にA子はマンションから飛び降り自殺を図り、顎が砕けて危篤状態に陥った。その夜、幼稚園の時にA子を捨てた母親が訪ねてきて、A子が危篤状態ということを伝えたが「この子は私がいても喜ばない」と言って、A子に会うことも無く帰ってしまった。
奥田氏はA子の「どうでもいい命」という口ぐせを思い出し、この言葉は母親をはじめ周りの大人がA子に言ってきた言葉ではないかと思った。
人間は縦だけでなく横にも成長する
どうにかA子は一命を取り留め、退院してから何年か経った時、「3割は生きようと思えるようになった」と言うようになった。理由を聞いたら「まだ、死にたいけれど私が死んだら教会にいる子供たちに悪い」と言った。
奥田氏はA子を通じて、人間は縦の成長だけでなく、横の成長もあることを学んだ。能力が高まる縦の成長も大事だが、人間関係を広げる横の成長が生きる力につながっているという。学校教育では縦の成長にばかり目が行きがちだが、子供たちの横の成長も見守ってほしいとする。
<パネルディスカッション>
パネルディスカッションでは3人のパネリストが、それぞれの立場から報告。コーディネーターは参加型システム研究所所長の半澤彰浩氏。
子供が安心して人間関係を作り合うことができる場所を
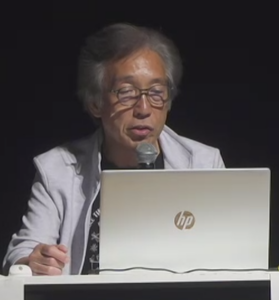
西野博之氏
川崎市で学校に行かない子供のフリースペースを開いて40年になる西野氏は「学校に行かない子供が見ている世界」をテーマに語った。
「子供は生まれながらにして一人の人間であり、大人と同様に権利の主体であるため差別されるようなことは、あってはならない」と西野氏は語る。にもかかわらず子供への差別や虐待が無くならないのは子供を知識も経験も体力も足りない未熟者として大人が捉えているからだとする。
川崎市では2001年4月から「子どもの権利条例」を施行。第27条には「子どもには安心して人間関係をつくりあうことができる場所が大切」と記されている。この条例の具現化を目指して、子供たちがやってみたいことを挑戦できる場所として青少年教育施設「川崎市子ども夢パーク」を2003年に建設した。
安心して失敗することができる場所を子供たちに
西野氏は教育と福祉の融合として、子供の育ちには「遊ぶ(play)」「学ぶ(learn)」「ケア(care)」の3要素が必要と川崎市に求めてきた。夢パークでは禁止事項のない「プレーパーク」と学校に居場所を見出せない子どもが集う「フリースペースえん」がある。プレーパークでは失敗した時こそ成長するチャンスとして、安心して失敗できる環境づくりが構築されている。
今の学校教育制度は疲労しているのではないかと語る西野氏。学校に適応できない子供に問題があるわけでなく、子供に適応できない学校教育に課題があるのではないかとする。重要なのは公立学校の改革として、本気で学校を変えたいと願い活動をしている。
増え続ける小中学生の不登校や長期欠席
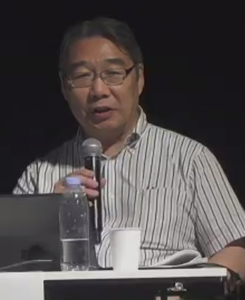
前川喜平氏
子供たちは社会の中の存在であり、社会全体で支えるべき存在と考える前川氏は「教育・学校を変える、地域社会で子どもたちを育てるとは」をテーマに語った。
「教員が楽しくなければ、子供たちが学校を楽しい場所だと感じられない」と語る前川氏。そのため、現代の日本では自己肯定感が低い子供が育っており、自殺率も高くなっているという。2023年には不登校の小中学生が約35万人を記録するなど急激に増加しており、病気による長期欠席も10年前と比べて約3倍に増えている。これは、うつ病などが原因で長期欠席の子供が増えていることが考えられる、
学校は子供にとって安心できる場所になっているか
こうした増加の背景には学校が子供にとって安心できる場所でないことが挙げられる。学校は苦しんでいる子供たちを受け止める場所であってほしいが、その役割を担うべき教員も苦しんでいるのが現状である。
学校は地域のものであり、その中心に子供がいなければならない。そして、子供の成長を手助けする教員と、それを支える保護者や地域住民という形で作られることが学校の本来あるべき姿ではないかとする。
互いに自分の意見を出し合うオランダのポルダー・モデル
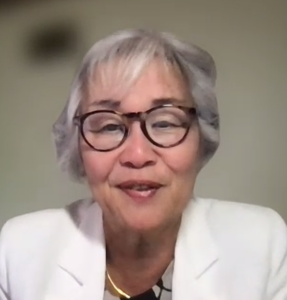
リヒテルズ直子氏
1981年に日本を出て、さまざまな国を巡り、1996年からオランダで生活しているリヒテルズ氏は、オランダに学ぶ公教育のあるべき姿について「子どもたちに自由と責任を育てる教育」をテーマにオランダからオンラインで語った。
オランダにはポルダー・モデルという考えが定着している。さまざまな考えを持っている人がいる中、考えが対立したままだと解決策が見出せなくなる。そこで互いの意見を率直に出し合い、共通項が見えてきたら妥協策を見出していく。
オランダの学校は子供の頃から話し合いを通して、Win-Winの道を探れるように自由と責任の意味を教える場所となっている。小学校は一斉に入学するのではなく、4歳頃になると週2~3回、小学校に通い始める。4歳から5歳の幼児グラスには子供の名前が書かれたボードが掲げられており、ここに「牛乳を配る」「花に水をあげる」など、自分がやるべきことを貼り付けていく。どの作業を誰が行うかは友達と話し合いながら決めるが、こうしたところからボルダー・モデルの考えを根付かせていく。
「不寛容の拒絶」と「差別の拒絶」を掲げていじめの傍観者にならない
2006年にオランダではシチズンシップ教育が義務化され、文科省は学校で生徒に教えなければならないこととして、「表現の自由」「平等」「他の人への理解」「寛容」「自律」「不寛容の拒絶」「差別の拒絶」の7つを示した。この中でリヒテルズ氏は「不寛容の拒絶」と「差別の拒絶」に着目する。世の中で不寛容な事態や差別が起きている時、自分は関わっていなくても社会の一員として、拒絶の態度を示して止めることが、いじめの防止などにつながっている。
日本の学校は難しい状態になっているが変わる道はあるはずと語るリヒテルズ氏は、学校が社会を変えるための突破口となることを期待する。