近年、図書館に「ゲーム」を導入する動きが活発だ。様々なゲームを所蔵し、貸出を行ったり、館内で遊べるようにしたり、イベントも開催されている。
“ゲームは読書の時間を奪う”イメージもあるかもしれないが、日向教授によると図書館に足を運ぶきっかけとなるのはもちろん、学ぶための資料としても意義があるという。
-図書館におけるゲームの導入はどのように広まっていますか。
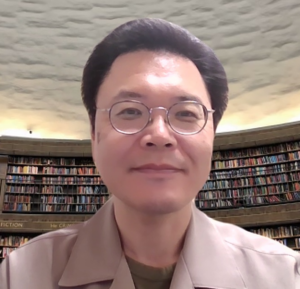
都留文科大学 教授 日向良和氏
日向 2018年は、ボードゲームのイベントをしている国内の公共図書館は100館未満でした(※1)。コロナ禍で一旦縮小しましたが、2023年に初開催した「ゲーミング図書館アワード」(※2)では公共図書館や学校図書館でも広がっていました。
背景にはコロナ禍以降に公共図書館への来館者が戻ってこないという課題があり、来館者を増やす起爆剤としてゲームに期待が寄せられたと考えています。
-学校図書館でゲームを導入する理由は。
日向 やはり学校図書館の活性化です。特に中高生の読書推進について社会全体で取り組まれる中で、これまで足を運ばなかった生徒たちにも来館して欲しい、特定の生徒ばかりの場ではないようにしたい、ということが多くの学校図書館でゲームを導入する際の目標になっています。
実際に、ゲームの楽しさが学校図書館に来るきっかけとなり、友達づくりにもつながった事例があります。
-読書推進としてはどのように有効でしょうか。
日向 ゲームは読書と結びつく要素が多いのです。例えば、歴史的な出来事をもとにしたり、小説をゲーム化したものもあります。ゲームのテーマに関連した本を子供に紹介することで、本を読むことにつながり、本でゲームの世界観をより楽しめるようになり、さらに本の内容への興味が深まる、といった循環が生まれることもあります。
学校図書館としては、来館のきっかけに留まらず、さらにそこから読書や探究につなげたい、といった願いがあると思うので、そうした事例を明らかにしていくことが今後の課題と言えます。
-小学校の場合はいかがですか。
日向 読み聞かせや図書の授業などが行われている小学校では、すでに児童が学校図書館を利用しているため、今のところゲームを導入しているところは少ないです。
ただ授業の中で楽しみながら学べる教材としてゲームを使うことはあると思います。そうしたゲームを学校図書館の資料にすることもできます。
また本を静かに読むことが苦手な子供にとって、ゲームがあると“学校図書館は楽しい時間を過ごせる場所である”というメッセージになり、来館しやすくなるでしょう。
小学校で遊びやすいものとしては棒を抜き取るバランスゲーム「スティッキー」や、カタカナ語禁止で言葉を説明する「ボブジテン」などがあります。勉強に近づきすぎるとつまらなくなってしまうので要注意ですが、学びのきっかけになるゲームも多いです。
-従来の学校図書館の資料に加え、ゲームを導入するのはハードルが高いようにも思います。
日向 教員が学校図書館で子供たちに身につけて欲しいことや取り組みたいこと、例えば小学校低学年なら“読む力”をつけていく、中高生であれば、人間関係や社会に対応する力を身につけるといったことと、ゲームの内容や特徴を合わせて考えることが重要です。
現在推進されている探究活動のために学校図書館の資料の充実がますます重要となる中で、コンテンツそのものの幅を広げることが必要になっています。
学校図書館の資料には、音楽や映像も含まれます。それぞれ表現方法が本と異なっているだけと考えれば、そこにゲームが加わることも十分考えられますし、本以外にも幅広い選択肢があることはとても重要です。
本を読むことが苦手な子供でも、ゲームに記載されたテキストを読んで“読む力”をつけたり、知識を得るなど、ゲームを通して本を読むのと同じような効果や知識を得ることが期待できます。
ゲームならではの特徴もあります。読書は1人で行うものですが、ゲームは遊ぶ相手があり、人とのコミュニケーションが必ずある。ルールがあるので、それを守ってコミュニケーションを図り、規範意識を育てます。
なお、学校図書館には居場所としての役割もあります。例えば埼玉県立飯能高等学校の「すみっコ図書館」は、館内で生徒が過ごしやすくなる取組の一つとして、ゲームも提供しています。
管理職や保護者の方にゲームの導入の理解を図る際には、実際に遊ぶ体験をしてもらうと同時に、このような教育的な要素やメリットを知って欲しいと思っています。
※1 高倉暁大氏の調査によると、ボードゲーム企画が開催された図書館は全74館(2018年10月調べ)から、150館(2023年11月調べ)まで増えている
※2 「ゲーミング図書館アワード」…日向教授、高倉氏も所属する団体「図書館とゲーム部」主催。例年秋に開催される「図書館総合展」で受賞者が発表されている
教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年9月15日号掲載
-学校でのゲーム導入について、日向教授に具体的に伺いました-
ポイント① 選書と同様、ゲームをどのように選ぶのかは重要です。
学校図書館では、アナログゲーム(ボードゲームやカードゲーム、TRPG※2など)が向いており、デジタルゲームは時間の管理が難しいと考えています。
ポイント② 具体的な選び方としては、休み時間の中で完結できる、10分~15分程度の短い時間でプレイできるものを選ぶ、またテーマが子供たちの年齢に合っているもの、学んで欲しいことと合致しているか、ルールが難しすぎないか、といったことも検討します。
ポイント③ 自校のルールを決めることも大切です。例えば、学校図書館内や教室のみで貸し出しを行ったり、遊べぶことができる。家へ持ち帰らない、きちんと片付ける、ケンカはしない、などが挙げられます。
ポイント④ 紙のボードゲームはたくさん遊べば傷みますし、駒やサイコロ等がなくなりやすく、メーカーが売り切れば再販しないものも多い。1冊を長く読む本とは違って、壊れたり欠損すれば新しいものを買う、という発想も必要です。
いま、学校図書館の資料の充実を図るために、地域の公共図書館との連携がますます必要になってきています。
福岡県立図書館では図書館や学校といった教育機関向けにゲームの貸し出しを行い、読書推進に役立てています。学校で初めて導入する際は、このような公共図書館から貸出を受けて試したり、遊び方を公共図書館の方に教えてもらうといった形でも、可能性を広げていけるのではないでしょうか。