EDIX東京2025が4月23~25日に開催され、3日間で2万3858人が来場した。公開授業は3本開催。東京学芸大学附属小金井小学校は6年国語で物語『帰り道』(光村図書)を題材に、児童が生成AIを活用する授業を公開した。
『帰り道』は登場人物「律」と「周也」のそれぞれの1人称で書かれ、視点の違いに着目して人物像を捉える内容。児童は前時、それぞれの視点に分けて書かれていることの効果について討議済で「同じ場面での2人の気持ちの違いがわかる」「感じ方で2人の性格がわかる」等と考えた。
公開授業では生成AIに学習されない設定で物語全文を読み込ませ、2つの視点を合体させた文章を作成し本文と比較した。

2人の文章の視点で書かれた物語を生成AIで合体
まず鈴木秀樹教諭が生成AIで視点を合体させた文章を児童に提示。それぞれの視点で書かれていることの効果が、合体させた文章でも表れているかどうかをグループで話し合った。
児童は「一方の視点が多すぎる」「気持ちやすれ違いがわかりにくい」等と指摘。
次に、児童も生成AI機能を利用できるtomoLinks「チャッともシンク」を使い、2つの視点で分けて書くのと同じ効果を出せる合体版の作成に各自で挑戦。

児童1人ひとりが生成AIを使い「合体版」の作成に挑戦
児童は「2人の気持ちをわかりやすくして」「この場面の感情をより詳しく」「三人称にして」等とプロンプトを工夫。デジタル教科書の本文と読み比べたり、どのような視点で合体させたのか生成AIに尋ねている子もいた。
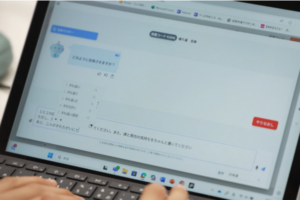
プロンプトを工夫してAIの文章を改善
上手くいった点やそうでない点、プロンプトの工夫を情報交換する中で「合体ではなく並列されているだけ」「的確な指示をしないと文章が変わらない」等と生成AIの本質に迫る指摘もあった。
納得できる文章を作成できた子もそうでない子も、本文の魅力をより感じることにつながっていた。
2つの視点から書かれた本文とAIで視点を合体させた文章とを比較することで、表現の効果や教材の魅力により迫ることができるのではないかと考えた。
AIの文章になぜ納得がいかないか、どう改善するのかという視点でプロンプトを考えることは、自分が教材のどこに魅力を感じているのかを認識するという国語の学習につながった。
担当学級の子供たちは、AI経験に差はあるものの、同じ課題に取り組むと友達の工夫が見え、経験がない子も学び合いによって習得が早まる。AIのすごいところやダメなところを共有しながら、AIに対し冷静に捉える姿が見られた。
授業の目的を達成するためにAIを使うこと、AI自体を学ぶ場面や使い方を学ぶ場面を入れつつ、各教科等の学びにおいて使うことを意識して活用している。「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」でも各場面を組み合わせたり往還したりしながら活用することが示されている。
子供たちをAIのよき使い手として育てるためには意識的にAIの様々な面を経験させること、間違っている場合もある等ズレを体験させることが必要。また、まずは教員が使ってみせ子供に示すという経験を積まないと誤った使い方をする子も出てくるだろう。
現在は授業でのみ使っているが、今後は日常生活で間違えないように使う場をどう整えていくかにも取り組んでいきたい。
関連:「まちラップ」で地域を表現 世田谷区立駒繋小学校――EDIX東京2025・公開授業
深い学びをもたらす授業事例 塩尻市・渋谷区・調布市立多摩川小学校――EDIX東京2025・特別講演
教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年5月19日号