「第5回 情報活用授業コンクール」(主催:公社・全国学校図書館協議会)の受賞者が今年5月に決定し(本紙7月21日号10面に掲載)、8月25日、東京・千代田区のキハラ㈱CCフロアで表彰式と受賞者発表会が開催。3校の実践が紹介された。
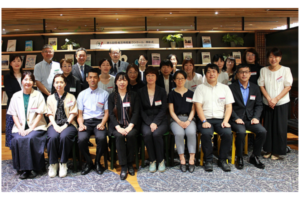
受賞者と主催者・審査員が参集
優秀賞・情報活用推進校
横須賀市立田浦小学校(神奈川県)
学校図書館のこれまでの取組や1年の国語、6年「理科-大地のつくり」の授業実践を発表した。理科では実物を見たり実験することを大切にしている。那須塩原の化石を取り寄せて授業をスタート。学校の近くの地層も示し、児童は縞模様になっていることに気付く。ダーウィンの本を紹介し、海に沈んでいない場所が、なぜ縞模様になるのかを考えた。児童は砂が風に運ばれたと仮説を立て、サーキュレーターで砂が風に飛ぶかどうかの実験を行うなど、調べる・見る・作っていく・専門家に聞きに行く、といったプロセスをたどる実践を紹介した。
発表者の一人である坂本幸太郎教諭(現・長浦小学校司書教諭)は、「1年生、6年生の実践とも、人と情報がつながることで“やってみたい”“調べてみたい”という好奇心が生まれることが分かった」と語った(同校は2025年4月より長浦小学校と統合)。

実践を発表(写真は田浦小)
優秀賞・キハラ賞
杉並区立高井戸中学校(東京都)
1年「社会科-ナゾトキ~授業で気になったこと、調べてみました~」の授業実践。授業中に生徒自身がさらに知りたいと思ったことを、各自がテーマ化し、長期休業中に取り組んだ。記入カードの工夫、資料の活用、学校司書や公共図書館との連携を行った。
優秀賞・情報活用推進校
京都先端科学大学附属中学校高等学校(京都府)
高校2年「論理国語-多様性を問う 新聞記事のジェンダー表現」の授業実践。新聞はブログ等とは違い、最新の情報を客観的な視点で知ることができる。また国語辞典が改訂するたびに時代を反映した語釈になることも交えた実践を行った。
なお「第6回情報活用授業コンクール」の応募期間は2026年2月1日~4月5日(当日消印有効)https://www.j-sla.or.jp/contest/jouhoukatsuyou/jouhoukatsuyoujugyou6.html
教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年9月15日号掲載