今年で30年目を迎えたNEW EDUCATION EXPO2025が6月5~7日に東京・サテライト会場で、6月13・14日に大阪で開催。東京会場の講演を一部紹介する。
「校務DX最前線~学習eポータル等との連携を通じ~」では3市が事例を報告。ともに校務支援システムは内田洋行「デジタル校務」、学習eポータルは「L-Gate」を導入している。ファシリテーターは藤村裕一氏・鳴門教育大学教員養成DX推進機構長。
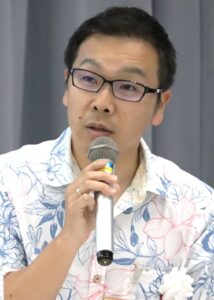
茅ヶ崎市教育委員会教育総務課政策担当 行川充主査
2023年度に統合型校務支援システムをクラウド化し、昨年度より運用を開始。校務系ネットワークはデータセンター経由、学習系は1Gbpsのローカルブレイクアウトで整備し、全校にIPフォンを配備。今年度末に学習用の11㌅iPad(A16)を導入予定である。
校務DXによりデータ連携、状況把握、事務軽減の3点が改善。
データ連携では、学籍情報をCSV形式で校務支援システムに取り込み作業時間と入力ミスを削減。校務支援システムの情報は学習eポータルを起点に各種システムと連携し年次更新作業が削減され、市内転居時には所属情報の更新後即時に転校先で児童生徒情報を確認できる。
状況把握の面では、欠席連絡システムの情報を職員室のモニターで共有。担任が教室で校務支援システムに出欠情報を入力。連絡がない場合はIPフォンで職員室と連携し、保護者への確認を迅速に行える。保健室でも校務支援システムから情報共有が可能だ。
事務軽減では、校務支援システムに出席確認として健康観察簿を入力すると出席簿が自動作成され、担任と養護教諭の負担が軽減。QRコードによる出退勤管理で紙の出勤簿や押印が不要となり、教育委員会の児童生徒名簿作成やデータ収集も効率化した。
データ活用も推進。事業者との協議を通じて活用方法を模索しており、データ蓄積の意義を教員にも示し、入力の動機付けを行っている。昨年度の本市のデータ蓄積量は全国的に高水準で、教育委員会事務局職員のモチベーション向上につながった。
将来的にはネットワーク統合によるセキュリティ対策の強化、災害時のレジリエンス力向上を目指す。複合機やデジタル採点システム、デジタルドリルについても試験導入をしながら検討しているところだ。また小中学校9年間のデータを分析して学校・学年別の傾向を把握し授業改善のエビデンスとしていきたい。国際技術標準「OneRoster」を活用し教育データの標準化と他自治体との連携による全体最適も推進していく。

坂戸市教育委員会学校教育課 菅裕太主任
2023年度に校務系と学習系のネットワーク統合、校務支援システムやツールのフルクラウド化を行い2024年度より運用。インターネットに直接接続するシンプルな構成となり、三層分離構成だった時と比べ、トラブル対応が容易になった。教員用端末も1台化し学習系はChrome、校務系はEdgeとブラウザを使い分けている。
データ連携を前提に校務環境を刷新したことで校務支援システムと学習eポータルを起点とした名簿データの自動連携が可能になり、進級処理や教員の異動、アカウント登
録は校務支援システムへの入力のみで完了。名簿の個別管理がほぼ不要となり作業負担が大幅に軽減された。
保護者連絡システムはスマートフォン向けアプリ「すぐーる」を導入。学校関連情報がアプリに一元化され、出欠連絡もアプリ上で行える。教育委員会と市長部局へ周知してアプリでの配信を基本とし、緊急でない連絡は児童生徒が学校にいない夕方に配信するなど運用面でも工夫している。
中学校に導入したデジタル採点システムにより採点時間が3日から1日に短縮され、教員からの反響も大きい。印刷機器は複合機に統合。スキャンデータはTeamsのフォルダに保存され、データ取り込みの手間が解消された。
課題は運用の効率化や教員のICTスキル向上。そのためにもICT支援員の配置などサポート体制の充実が求められる。教育委員会の人員不足も課題で指導主事の負担軽減が急務だ。学校徴収金管理のデジタル化は各校の運用が異なり統一が困難な状況がある。
今後は、導入したシステムの活用をさらに探り、今年度予定している学習用端末の更新を契機に教員の意識変化と校務DXの加速を図る。生成AIを教職員が利用できる環境は整いつつあり、教育委員会が効果を検証し活用を促進していく。

甲賀市教育委員会学校教育課 川﨑漸課長補佐
学習指導要領改訂を機に市内各校での校務環境の統一を目指し、2021年度に校務支援システムと学習eポータルを導入。段階的に校務DXを進めてきた。
23年度に校務支援システムと感染症情報システム、健康観察アプリを連携。教室で担任が健康観察アプリに情報を入力すると校務支援システムと感染症情報システムに自動送信され出席簿もボタン一つで作成できる。
Microsoft365 A5を活用し、従来のオンプレミスサーバーからフルクラウド環境へ移行。教員用端末を一台化し利用環境も拡充した。
24年度には保護者連絡アプリを導入。朝の電話連絡が激減し、校務支援システムとの名簿連携で年度更新作業も不要である。
校務支援システムをハブとしたシステム間連携により業務が改善。今後は中学校での自動採点システムの導入や出張・年次休暇の申請・承認のデジタル化を進める。

甲賀市教育委員会 宮治喜代司ICT教育指導員
Microsoftアカウントをすべての児童生徒・教員の識別IDとして一元管理することを目指し校務支援システムを基盤に児童生徒情報、端末情報、ID情報を集約。システム間連携が円滑化した。ライセンス管理や教員情報は教育委員会が、児童生徒情報は学校が日常業務で入力し役割分担を図っている。
毎朝30分のデータ点検によりデータの質を高め円滑な連携を強化。校務支援システムや学習eポータル、端末管理、Webフィルタリングの情報をCSVで集約し不備を確認している。
転出入状況の早期把握や、兄弟姉妹関係の情報から世帯数を把握するなど学校データを市全体のデータへと統一。端末の空き容量やOSバージョンも常時監視し管理負担を軽減。アップデート時もスムーズに対応できる。
データの形式を統一したことで教育委員会内でのデータ活用の幅が広がった。

藤村裕一氏・鳴門教育大学教員養成DX推進機構長
次世代校務DXはパブリッククラウドを前提とした環境整備により、学校の働き方改革、データ連携とその活用による教育活動の高度化、大規模災害時にも学びを継続するレジリエンス確保を図るものだ。
校務支援システムと学習eポータルをハブとして各種システムを連携し、ダッシュボードによるデータの可視化を通じてより良い教育の実現に向けた知見を導き出すことが期待されている。ダッシュボードは生成AIとBI(可視化)ツールを活用することで、より安価かつ容易に構築できるようになった。
レジリエンス向上にはネットワーク統合が必須であり、被災地での事例でもゼロトラストセキュリティやテレワーク環境の導入が有効であった。
ツールの導入に加え、テレワーク関連の規則整備や境界型防御に基づいた従来の規則の改定、文書管理規定の改善などルールの整備も不可欠。職員室にファイルが山積みされている現状はただちに改善すべきである。
DX推進の鍵は、熱意をもち周囲を巻き込むリーダーの存在だ。加えて持続可能な運用のためにはリーダーに過度に依存しない組織作りが重要。
5月に教育分野の認証基盤の在り方に関する検討会の取りまとめが公表された。全国的な共通基盤整備の検討が進む。
現状、各自治体では部分的な調達が行われ、システムを統合的に接続する全体最適の観点が十分に考慮されていない点が課題である。
この課題を解決するためにも、3月に策定された「初等中等教育におけるシステム間連携のための相互運用標準モデル(旧学習eポータル標準モデル)」に準拠し、システム間連携を前提に調達を行う必要がある。

次世代校務DXには全体最適が重要と指摘した
これらの取組には高度な専門知識が求められるため、従来の調達方法では対応が難しい。総務省の地域情報アドバイザー制度なども活用しながら、計画的かつ組織的に検討を進めてほしい。
教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年7月21日号